動物の法律として広く知られている動物の愛護と管理に関する法律(以下、動物愛護法)ですが、5年に一度その内容を審議し必要があれば改めています。
5回目の法改正が今年の2025年に行われる予定です。
法律と聞くとなかなかとっつきにくい印象を受けてしまいますよね。
私自身も動物愛護法のことを大まかには理解していたものの、詳しく説明を求められると手も足も出ない状態でした。
しかし、動物愛護法は私達にとって身近な法律です。
そして、時折法改正が行われその内容に対してたくさん議論が行われているということは、その内容にはまだまだ不足していることがある、ということですよね。
今回の改正を控えて議論すべきなのはどのような事柄なのでしょうか。
この機会に一緒に考えてみましょう!
動物愛護法とは

そもそも動物愛護法とはどんな内容の法律なのか、ざっくりと説明します。
動物の愛護と管理に関する法律は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
参考:動物愛護管理法の概要
日本における動物に関する法律は多くなく、と畜場法や家畜伝染病予防法、獣医師法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律などが挙げられます。
その多くは人間の生活を守るもので、動物を守る法律としては動物愛護法が主たるものとなっています。
現行の動物愛護法の概要
2025年3月現在の動物愛護法は以下の項目で構成されています。
①総則
②基本指針等
③動物の適正な取扱い
→①総則
②第一種動物取扱業者
③第二種動物取扱業者
④周辺の生活環境の保全等に係る措置
⑤動物による人の生命などに対する侵害を防止するための措置
④都道府県等の措置等
⑤動物愛護管理センター等
⑥犬及び猫の登録
⑦雑則
⑧罰則
参考:動物の愛護及び管理に関する法律
動物を愛護するという基本指針から始まり、動物虐待の防止や動物から人間に危害が加わらないようにする取り決めなどが定められています。
動物愛護法の今までの道のり

動物の愛護及び管理に関する法律は、1973年に「動物の保護及び管理に関する法律」として議員立法にて制定されました。
反対者数は0人だったというので、その必要性は議論の余地がないものであったということが想像できます。
1973年当初にできた動物の保護及び管理に関する法律は以下の項目で構成されていました。
①目的
②基本原則
③動物愛護週間
④適正な飼養および保管
⑤犬及び猫の引き取り
⑥負傷動物などの発見者の通報措置
⑦犬及び猫の繁殖制限
⑧動物を殺す場合の方法
⑨動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置
⑩動物保護審議会
⑪罰則
⑫附則
参考:日本研究のための歴史情報 法令データベース 動物の保護及び管理に関する法律
条文を実際に読んでみると、その文字数は大変少ないものでとても簡素なものだったことが分かります。
1973年の施行後、26年の時を経て1999年に初めての法改正が行われました。
その際に現在の名称である動物の愛護及び管理に関する法律に変更されました。
各法改正時の具体的な内容については、以下の表にまとめます。
| 西暦(和暦) | 改正内容 |
| 1999年(平成11年) | 動物の愛護及び管理に関する法律に名称変更 動物取扱業種を指定 動物取扱業の規制 飼い主責任の徹底 虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大 罰則の強化 |
| 2005年(平成17年) | 動物取扱業の規制強化 特定動物の飼育規制の一律化 実験動物への配慮罰則の強化 施行後5年ごとを目安に法改正を検討することに |
| 2012年(平成24年 | 動物取扱業の適正化 終生飼養の明文化 罰則の強化 |
| 2019年(令和元年) | 責務規定の明確化 第一種動物取扱業の適正化 罰則の強化 特定動物の規制強化 マイクロチップの装着などについて 畜産に関する文言が初めて追加 |
1999年に動物取扱業というものが初めて指定されたのですが、法改正ごとに動物取扱業の規制強化が行われ、罰則の強化も行われています。
この部分に関しては、民間での議論が活発で規制強化に繋がりやすかったのではないでしょうか。
また、その他にも特定動物に関する規制強化やマイクロチップ装着についてなど、改正を重ねるごとに法律の内容は充実してきたことが分かります。
愛護動物とは?

動物愛護法の中で保護される”愛護動物”は明確に決められています。
この法律の中で言う愛護動物とは、以下のものを指します。
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
上記はぜひこれは覚えていてほしい部分です。
いえばとというのは、カワラバトが家禽化したもので、ドバトや飼い鳩とも呼ばれるとのことです。
1に分類されるものは産業動物や使役動物、愛玩動物として私達に馴染みの深い動物で、人が専有しているかを問わず愛護動物となります。
また、人が飼っている、企業が飼育しているなどで占有される動物は、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものであれば、1に記載されている動物以外でも愛護動物となります。
反対に言うと、人が専有していても両生類や魚類などは愛護動物に含まれません。
参考:資料1 対象動物種の範囲
動物取扱業とは?

一般家庭で飼育されている動物が虐待や遺棄をされる事例はもちろんありますが、動物を取り扱っている業者が動物に対して酷い扱いをしているということが問題視されてきました。
そこで、1999年の法改正では動物に関連する業種を指定し、それらに対して監視の目が届きやすいようにしました。
動物取扱業は2種類あり、第一種動物取扱業は営利目的であるもの、第二種動物取扱業は営利目的でないものというふうに分けられます。
第一種動物取扱業に指定されているものは以下の7業種です。
| 業種 | 業者の例 |
| 販売 | ・小売業者・卸売業者・販売目的の繁殖又は輸入を行う者 |
| 保管 | ・ペットホテル業者・美容業者(動物を預かる場合)・ペットシッター |
| 貸出 | ・ペットレンタル業者・撮影等のタレント・撮影モデル・繁殖用などの動物派遣業者 |
| 訓練 | ・動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
| 展示 | ・動物園・水族館・移動動物園・動物サーカス・動物ふれあいパーク・乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 競りあっせん | ・動物オークション(会場を設けて行う場合) |
| 譲受飼養業 | ・老犬老猫ホーム |
第二種動物取扱業者として規制を受けるのは、営利性を有しない動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うものと定められています。
ここで、第一種、第二種動物取扱業者ともに、規制を受ける業種の中に「実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。」という趣旨の文言が入ります。
動物取扱業の規制の中に、実験動物や産業動物は入っていないのです。
動物愛護法の不足している部分
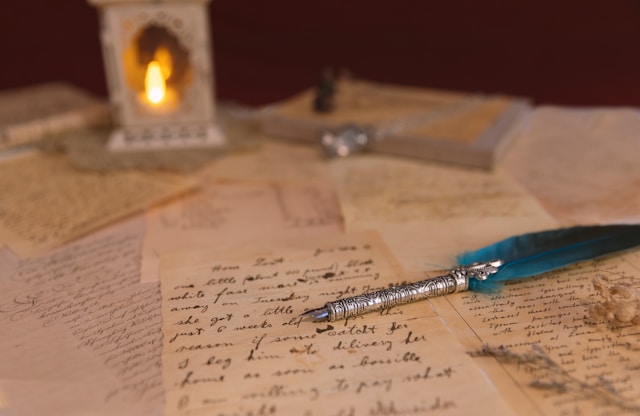
改正を重ねるごとにその内容が充実してきた動物愛護法ですが、どこの部分を改正する必要があるのでしょうか?
正直に言うと、不足している事柄だらけです。
改善しなければならないと思われるものを一部ご紹介します。
ペット関連では…
- 動物虐待事件の多さ
- ペットブームの裏で発生する遺棄事件
- 過剰繁殖問題
畜産動物関連では…
- 屠殺方法の問題
- 飼育ケージの広さに関する問題
- 無麻酔科の避妊・去勢・断尾などが横行していることの問題
実験動物関連では…
- 代替方法が進んでいないことの問題
- 殺処分に関する問題
野生動物関連では…
- ペットに向かない動物の取引に関する問題
- 密猟の問題
日本を代表する動物の愛護・福祉団体は、共同で改正案をまとめていますのでそちらもぜひご参照ください。
改正が必要な内容としては以下のように記載されています。
動物愛護法から動物福祉法への転換
対象動物種・業種の拡大
産業動物に関する条項を追加
動物実験代替法の利用を義務化、3Rの徹底
輸送に関する条項を新設
動物を殺す場合の方法を改善
罰則の明確化
虐待された動物の保護
第一種動物取扱業の規制を強化①移動展示・移動販売の禁止
②自治体職員の”動物Gメン”化
すべての動物の所有者又は占有者の責務・禁止事項の強化~飼育できる動物を限定するホワイトリスト制の導入を!~
不適切飼養の是正
その他の改正
1.第十条の次の除外規定を削除する(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るものおよび試験研究用または生物学的製剤の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節において同じ。)
2.動物の飼育者に対し、対人事故を起こした場合の報告を義務化する
3.8終齢規制について日本犬6種の附則を削除
参考:アニマルライツセンター 動物愛護法改正の重要ポイント
アニマルライツセンターなどの動物福祉・権利団体は、動物愛護法の改正があるたびに改正案をまとめ、国会議員に提出しています。
この改正案は、2025年の法改正でどれだけ反映されるのでしょうか。
今回の焦点はどこになるのか

動物取扱業に指定されている業者や個人の虐待、飼育崩壊などに関しては議論が活発で、今後も発展していくだろうと考えられます。
ただ、ザル法と呼ばれないために、きちんと法を遵守し違反者には罰則や改善指導を強化するべきだとは思います。
しかし、もっと犠牲の数が多く、法律で守られていない動物は何かと考えると、圧倒的に産業動物ではないかと思っています。
牛や豚、鶏などの産業動物はたしかに”愛護動物”として法律で守られています。
しかし、それらの動物が犬や猫と同様に守られてきたでしょうか。
私自身、最近知ってとても驚いたことがあります。
日本では鶏を屠殺する前の気絶処理(スタニング)が義務付けられていません。
アニマルライツセンターの調査によると、把握可能な日本の現状としては、85%が事前のスタニングなしで屠殺を行っているとのことです。
屠殺のため生きたまま吊り下げられた鶏は、当然意識があるので動き回ります。
そのためネックカットの際にうまく頸動脈を切ることができないと放血不良になり、生きたまま熱湯に湯漬けされることになります。
生きている状態で湯漬けされると、生体反応として皮膚が真っ赤に炎症を起こし売り物にならない状態になってしまうのです。
そうして廃棄された鶏の数は2024年で70万羽に上ったといいます。
参考:国内鶏肉の処理のレベル再び低下:屠殺に失敗し70万頭の鶏を生きたまま熱湯に入れ殺す
自分が知らないだけで、屠殺方法の不備により70万羽もの鶏が犠牲になっているとは思いもよりませんでした。
2017年では47万羽だったとのことなので、更に状況は悪くなっています。
ちなみに、スタニングが義務付けられているアメリカは日本の3倍の鶏肉の消費量がありますが、屠殺方法の不備による廃棄量は年間3万羽だといいます。
屠殺時のスタニングが義務化されている国としては、中国、フィリピン、マレーシア、インド、タイ、ベトナム、ブラジル、米国、カナダ、メキシコ、EUなどが挙げられます。
そんななかで、日本の動物愛護法の動物を殺す場合の方法に関しては、
(動物を殺す場合の方法)
第四十条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
3 前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。
と記載されています。
また、動物の殺処分方法に関する指針の内容については、
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認され ている通常の方法によること。
となっており、何ら具体的な方法は記載されていません。
欧州やアメリカなどのみならずアジア諸国でも規制がなされているのにも関わらず、なぜか日本ではこのようなことが未だに横行しています。
ただ、2019年の動物愛護法の改正において畜産動物に関する文言が初めて追加され、前進がなかった訳ではありません。
すでに畜産業者とコンタクトのある行政(家畜保健衛生所など)、屠殺場や食鳥処理場に立ち入る家畜保健衛生所職員などは、動物愛護法の指導を行うことが努力義務となりました。
しかし、日本の現状を見る限り、動物の福祉が改善されているとは到底思えません。
現在までの罰則適応例

ザル法と言われるほど動物愛護法は軽視されていますが、それでも今まで罰則が適応された事例は何度もあります。
まずは条文に記載されている罰則内容を振り返ってみましょう。
①5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
→愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合
②1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
→愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること
→みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること
→自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと
→排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者
③1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
→愛護動物を遺棄した者
となります。
では、実際の殺傷における判例を紹介します。
2017年、猫1匹の身体を多数回にわたって床に叩きつけるなどし、多発外傷による硬膜外出血及び脳浮腫により死亡させたとして、逮捕される事件がありました。
この判例では、みだりに猫を殺し、廃棄物である動物の死骸を捨てたとして、動物愛護管理法と廃棄物処理法の併合罪によって懲役1年(執行猶予3年)との判決が奈良地方裁判所にて下されています。
2016年、北海道にて飼育する馬に向けて猟銃を発射し、死亡させたとして動物愛護管理法違反として逮捕される事件がありました。
理由なく飼育していた馬を殺したことで、この判例では懲役1年(執行猶予4年)の判決が下されることになりました。
動物虐待は暴力行為などによる死傷だけでなく、ネグレクト(飼育放棄)のような虐待にも当てはまります。
次に、死傷ではなく虐待の判例を紹介します。
2018年に名古屋で起きた虐待事件では、45匹の猫を排泄物が堆積した場所で飼育したとして、動物愛護管理法違反で被告人2人に略式命令が下されました。
この判例では、両名ともそれぞれ10万円の罰金を課せられています。
2018年に岐阜県で起きた虐待事件では、被告人の所有する物件で2匹の犬に対し、エサや水を与えずに衰弱させました。
また排泄物が堆積した場所で飼育したとして、動物愛護管理法違反として判決が下され、罰金10万円が課せられています。
動物の保護及び管理に関する法律が立法された当初の1974年は1年間で13件の受理件数に留まっていましたが、2007年には1年間で50件を超え、2019年には163件、2020年では156件、2021年では285件もの動物愛護法違反者を受理しました。
罰則のない義務違反はどうなる?

動物愛護法の内容を見ていると、罰則の適応となる項目が案外少ないように感じませんか?
動物の愛護法違反となるけれども、罰則がない場合はどのような処置になるのか気になったので調べてみました。
条文の中では、「〜しなければならない。」と記載されている文章が多くありますが、特に罰則が定められていないことが多々あります。
そのような項目は、義務違反が発覚し次第、監督官庁から行政指導がなされる場合があります。
新潟県で行われている行政処分に関わる文書を見つけましたので、参考にさせていただきました。
まず、義務違反が発覚した場合、保健所長が改善指導を口頭または文書で行い、それでも改善が見られなければ改善勧告を行うことになります。
改善勧告は改善指導よりも強く、具体的な行動を取るように勧めることを意味します。
改善勧告に正当な理由なく従わない場合、措置命令を出します。
この措置命令事項に違反した場合は、告発することが可能です。
告発とは、第三者が犯罪事実を検察関係者に知らせて訴追を求めることを指します。
告発に関して、保健所長は悪質と認められる違反者に対しては、法務担当課及び警察署長と協議のうえ告発を行い、知事に報告すること、となっています。
上記の流れをまとめると以下のようになります。
義務違反発覚→改善指導→改善勧告→措置命令→告発
参考:動物愛護管理関係業務に関する不利益処分等の基準
人に対する法律であれば、被害を被った人が民事訴訟などを起こせば多額の賠償金を支払わないといけない場合もありますし、法による罰則規定などなくても法律は守ります。
また、訴訟を起こされたとなれば、その事実が知れ渡り社会的な立場が悪くなることもあるでしょう。
しかし、動物は自分で被害を訴え、訴訟を起こすことなどできません。
上記のような義務違反者に対する改善措置の流れはありますが、なかなか実行されない現実があると思います。
だからこそ、懲役刑や罰金刑に該当する事項をさらに細かく規定しておかないと、法律を厳格に守る風潮にはならないのではないでしょうか。
参考:罰則のない法律は、守らなくても問題ナシ?~努力義務規定の位置付けと対応~
海外の法律との比較
以前の記事でも記載したように、日本の動物に関する福祉(アニマルウェルフェア)は諸外国に遅れて大変遅れています。
その大きな理由として、国が主導する規制:法整備が全く整っていないという点が挙げられると述べました。
これは、世界的な動物保護協会であるワールド・アニマル・プロテクションが作成した動物保護指標にて、日本が最低ランクの評価になっていることからも分かります。
実際に、海外では動物に関する法律はどのようなものがあるのでしょうか?
以下のサイトの比較表がわかりやすいので参考にしてみてください。
参考:海外の動物福祉はどう進んでいるの? – 公益財団法人動物環境・福祉協会Eva
このように、愛護動物はもちろんですが、畜産動物についての福祉については雲泥の差です。
海外で実際に施行されている法律に目を向けて、日本の法律を見直していくことが動物福祉先進国への第一歩となるのではないでしょうか。
まとめ

そもそもですが、「動物愛護」という考え方は日本独特のものです。
愛して護る、というのは悪くありませんが、人間主体の考え方であって、動物主体ではありません。
世界的、特に欧米諸国では「動物福祉」という考え方が広くあって、動物のより良い暮らし、より良い生き方というものに焦点を当てています。
そのため、法律も動物目線で考えているために動物の先進国になることができたのでしょう。
いままでの動物愛護法の変遷を見てみると、立法された当初から徐々に内容が充実したことでたくさんの命が救われました。
生まれてまもなくの犬や猫がペットとして取引されることが少なくなり、犬や猫の殺処分数は大幅に減らすことに成功しました。
これは世論の高まりから実現したものだと思います。
しかし、日本の動物愛護、福祉を考えるとまだまだ改善すべき点が山積みです。
どの点を重要視するのかは意見が分かれますが、何かを問題視し考え続けることがいちばん重要なのではないかなと思います。
5年に一度は法改正の機会が与えられているのですから、日本の動物愛護・福祉の行方を皆で考え続けましょう。












