日本に外来生物法ができたのは2005年。
そこから20年の歳月が流れましたが、外来種問題は改善されたと言えるのでしょうか。
これまで、外来種とは様々な戦いが繰り広げられてきました。
今回は、外来種問題に関するさまざまな取組みや、今後どのように向き合っていけば良いのかを考えていきたいと思います。
日本に定着している外来種は多い

日本は島国なので、他の国々とは地理的に大きな隔たりを持っています。
他の国から日本を取り囲む海を飛び越えてやってくる陸上の動物はいません。
しかし、1900年代に入り日本が近代化されると、海路や空路の開拓によって海を超えて外国の外来種が運び込まれました。
定着せずそのままいなくなる外来種ももちろん存在しますが、中にはどんどん繁殖し生息域を拡げてしまうという問題が起こります。
個体数が増えるとともに農作物被害、在来種の減少や生態系の破壊といった被害も拡大していくことは想像ができるでしょう。
特定外来生物として指定されている種は、2025年時点において動物から植物まで、すべてをカウントすると全部で162種にものぼります。
また、被害を及ぼす恐れがあるがよくわかっていない未判定外来生物も52種が存在します。
参考:日本の外来種対策
外来種が引き起こす問題
- 捕食…在来種の捕食
- 競合…在来種と生息場所や餌資源を奪い合う
- 交雑…在来種と交雑することによって遺伝子汚染が発生する
- 食害…農作物等への被害
- 感染…感染症や寄生虫を持ち込む
外来種問題の関連法規

外来種の取り扱いに関しては、いくつかの法律が関連してくるので、正しい知識がないとうっかりと法律違反をしてしまうなんてことになりかねません。
外来種に関係する法律は、以下の3つがあります。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
この法律は略して外来生物法と呼ばれます。
外来生物法では特定外来生物の種の指定や、それらの扱い方について明記されています。
この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
この中では、特定外来生物を取り扱う際の禁止事項として飼養、栽培、保管、輸入、受け渡し、引き渡し、譲渡し、放出(逃がす)が挙げられています。
特定外来生物に指定されている動物は、基本的に触らないほうがよい、ということです。
ただし自治体により防除が認められた場合には、その防除可能な区域、期間で、決められた方法によって行うのであれば、必要な手続きを行った上で特定外来生物の移動や保管・保護、殺処分などが可能になります。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
この法律は鳥獣保護法と略され、野生鳥獣の保護や管理について定められています。
ほとんどの鳥と哺乳類はこの法律で守られているので、捕まえたり、殺したりすることはできません。
ここでポイントなのは、外来生物であっても鳥獣保護法の保護の対象になるということです。
しかし、先述した外来生物法では、鳥や獣が鳥獣保護法で保護されていても、外来生物の駆除が必要だと国や地方公共団体が判断し防除を行うという取り決めがなされた場合には、保護の対象外となり、捕獲することができるようになります。
また、鳥獣保護法でも狩猟鳥獣として指定された種は特定の期間、方法によって狩猟をしても良いと決められています。
その他にも、鳥獣保護法に則り必要な手続きを経て有害鳥獣捕獲として動物を捕獲することができます。
これは生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害などが生じている場合などに認められるものです。
基本的に野生動物は鳥獣保護法で守られていますが、その鳥獣保護法の狩猟鳥獣や有害鳥獣捕獲、外来生物法の防除の対象になっている場合は、捕獲などが認められるということです。
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法)では基本原則として以下の文言が記載されています。
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない
これは特定外来生物であっても当然ながら当てはまり、捕獲や保護・保管などをする際にもその動物をぞんざいに扱うと法律違反になるのです。
また、動物を殺す場合の方法として、
動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。
とあります。
これは、殺処分されることが多い特定外来生物について度々問題になる事項です。
日本で問題になっている外来生物
冒頭で述べた通り、日本で外来生物法が成立してから20年が経過しました。
この期間の中で、外来生物に対してはその数を減らすために様々な取り組みがされてきました。
そのなかでも対策に特に力を入れている外来種をいくつか紹介します。
アライグマ

アライグマはその見た目の可愛らしさからペットとして輸入されましたが、成長し大人になると気性が荒くなるということなどから屋外に放したり逃げた個体が繁殖し日本に定着してしまいました。
このアライグマとの戦いの歴史は長く、外来生物法ができた2005年から特定外来生物に登録されています。
令和4年度の大阪府における農作物の鳥獣別被害額はNo.1と甚大な被害を起こしており、日本の侵略的外来種ワースト100に指定されています。
参考:侵入生物データベース
特定外来生物に指定されているのはアライグマとカニクイアライグマという2種がいますが、日本に定着しているのはアライグマのみのようです。
2種とも哺乳綱食肉目アライグマ科アライグマ属に属します。
北米が原産で、北米では生息数が減少しているため、アメリカの州によっては保護の対象とされている場合もあります。
外見はたぬきと似ていますが、たぬきに比べ全体的に白っぽい部分が多いこと、尻尾が白と黒のしましま模様であることなどで判別が可能です。
また、かかとを付けて歩く蹠行性(しょこうせい)という歩き方をするため、アライグマが歩いたあとには人間の手のような5本の指がくっきりと残ります。
泳ぐことが可能で、後ろ足で立つこともできますし木登りも得意です。
アライグマという名の通り手を器用に使って水の中で食べ物を洗う姿を想像する方が多いと思いますが、実は目があまり良くなく、発達した触覚を頼りに生活しているため手を使用することが多いといわれています。
被害の現状
アライグマが引き起こす被害は、農作物被害から感染症の媒介、在来生物の迫害など多岐に渡ります。
- 農作物被害
- 家屋の損壊
- 糞尿による衛生被害
- 感染症の媒介
- 在来種の迫害
- 子供やペットに危害が加わる危険性
令和4年度における大阪府での農作物被害額は5000万円にものぼり、鳥獣別被害額No.1です。
近畿圏の他の県においてはイノシシやシカによる農作物被害が多いですが、その次に被害をもたらしているのはアライグマです。
参考:令和4年度野生鳥獣による農作物被害状況(近畿農政局管内)
アライグマは雑食性で、野菜や果物が大好き。
特にスイカ、とうもろこしの被害が多い傾向にあります。
アライグマによる食害は特徴的で、メロンやスイカなどは穴を空けその中に手を突っ込み中身を掻き出して食べるため、ひと目でアライグマによるものだと判断することができるといいます。
人間にとって美味しく感じる果物や野菜は、野生動物にとっても魅力的な食材であることは疑いようがありません。
形が悪いなどで廃棄される農作物は野生動物を惹きつける誘引剤となってしまっていることもあるそうです。
侵入を防止するための柵を設置しても、たやすく飛び越えたり、穴をあけるなどするため、侵入を防止することはなかなか容易ではないそう。
参考:アライグマ、ハクビシン等中型獣類による農作物被害対策について
また、アライグマは日本の在来種や固有種を食べてその個体数を減少させてしまうこともあります。
イシガメやクサガメがアライグマによって噛まれ四肢が欠損した個体はよく報告されるとのことですが、ミシシッピアカミミガメの四肢が欠損した個体はあまり見かけないとのこと。
どんな理由でその差が出ているのかはわかりませんが、日本の在来種であるイシガメの個体数減少の一因となっていることは間違いないでしょう。
また、カメのみならずカエルやサンショウウオなども好んで食べるため、多くの種に影響が出ています。
日本に生息しているアライグマの正確な個体数は分かっていませんが、増加傾向にあるのは間違いないようです。
参考:アライグマによると思われるミシシッピアカミミガメの前肢食害:屋外人工池での一例
参考:農研機構
日本におけるアライグマの現状
- 日本の侵略的外来種ワースト100
- 令和4年度における大阪府での農作物への被害額は鳥獣別No.1
- アライグマの個体数は増加傾向
マングース

マングースは世界の侵略的外来種ワースト100、日本の侵略的外来種ワースト100に認定されており、アライグマ同様に2005年から特定外来種に指定されています。
初めて日本にマングースが導入されたのは1910年で、ネズミやハブの駆除を目的としていましたが、ネズミやハブを狙うことは少なく、反対に日本の希少な在来種・固有種を襲うという問題に発展しました。
マングースは今も日本に定着していますが、奄美大島での根絶が発表され大きな話題となりました。
奄美大島ほどの大きな地域で根絶ができたということは、世界規模の成功事例として他の外来種対策の推進に寄与しています。
2005年に外来生物法によって特定外来生物に分類されたのはジャワマングースでしたが、その後日本に定着しているのはフイリマングースであることが明らかとなり、2013年にフイリマングースが改めて特定外来生物に指定されました。
ちなみに元の生息地である中国では絶滅が疑惧される危急種に指定されているとのことです。
東南アジアが原産で、フイリマングースは生息圏が狭いため、生息密度は高い傾向にあります。
肉食性が強いイメージですが、食性は雑食性で、哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫、果実まで何でも食べるとのこと。
日本に定着しているフイリマングースは昆虫を主な餌資源としていることが判明しています。
フイリマングースはイタチ科なので、野生のニホンイタチやフェレットと同じような体型で胴は細長く、四肢が短いのが特徴です。
腹部を除いて黒〜褐色と黄白色の毛に覆われており、頭部は細長く、鼻先は尖っています。
フイリマングースは尾が長く、体長(鼻先から尾の付け根まで)と同じくらいの長さがあります。
九州にも生息しているテンは、イタチやフイリマングースよりも体が大きいため見分けがつきます。
逆にニホンイタチはフイリマングースよりも一回り小さいのが特徴です。
参考:沖縄諸島の外来種
被害の現状
フイリマングースが導入されたのは沖縄諸島や奄美大島で、固有種が多い地域です。
元々肉食獣が少ない地域に突如として現れたフイリマングースは、固有の在来種であり特別天然記念物のアマミノクロウサギやケナガネズミなどを捕食するようになりました。
また固有種への被害のみならず、養鶏への被害やバナナ・マンゴー・柑橘類などへの食害も見られるそうです。
日本におけるフイリマングースの現状
- 日本の侵略的外来種ワースト100、世界の侵略的外来種ワースト100
- 奄美大島では根絶を達成するも他の地域にはまだ定着している
- 日本の固有種を捕食している
ミシシッピアカミミガメ

ミシシッピアカミミガメはミドリガメとしてペットショップでも売られ、大衆的に飼育されることが多かった種です。
しかし想像以上に長生きをする種でもあり、様々な要因から野外へ放たれる個体が多く、日本各地に定着してしまいました。
ミシシッピアカミミガメについては、生態系等に被害を及ぼすことが懸念されることから、2005年の外来生物法の施行に合わせて法律に基づく特定外来生物への指定が検討されました。
しかしその際には特定外来生物への指定は見送られ、近年の2022年に行われた外来生物法の改正時に「条件付特定外来生物」に指定されました。
また、ミシシッピアカミミガメは日本の侵略的外来種ワースト100に認定されています。
ミシシッピアカミミガメは爬虫綱カメ目ヌマガメ科アカミミガメ属アカミミガメに分類されます。
原産地は北アメリカで、アメリカ合衆国東南部からメキシコまで生息。
食性は雑食性で魚類、甲殻類、水生昆虫、水草等を食べます。
在来種のニホンイシガメよりもかなり大きくなり、ミシシッピアカミミガメは顔の横に赤いラインが入っていることが特徴的です。
クサガメなど他の亀にも当てはまることですが、ミシシッピアカミミガメのオスは成長すると体が黒くなってくる黒化現象(メラニズム)というものが起きます。
この黒化現象が起こっている場合は耳の赤いラインも消失たように見えるので、一見すると他の種類ではないかと見間違えるかもしれません。
被害の現状
ミシシッピアカミミガメが日本に生息しているために起こる問題点としては、生息ニッチが似ている同じヌマガメ類の生息場所や餌が競合することにより在来種の数が減ってしまうということです。
特に日本の在来種であるイシガメとは生息場所や餌を争っており、イシガメの数が激減しています。
なお、クサガメも日本国内でよく見かけますが、元は中国や韓国が原産の外来種です。
定着地域では在来の水生植物、魚類、両生類、甲殻類等を食べてしまうため、生態系に影響をもたらしています。
農作物被害としてれんこんの食害に加え、観賞用のハス、ジュンサイやヒシの食害などもあります。
環境省では、アカミミガメ対策推進プロジェクトを公表し、アカミミガメ対策に向けた取組を強化しています。
全国の野外に定着しているアカミミガメの個体数調査が行われ、2016年時点では約800万匹にも登るという研究結果がでました。
参考: (お知らせ)全国の野外におけるアカミミガメの生息個体数等の推定について
2016年から約10年の時が流れましたが、その個体数はどれほどの変動があったのでしょうか。
日本におけるミシシッピアカミミガメの現状
- 日本の侵略的外来種ワースト100
- 2022年、条件付特定外来生物に指定
- 2016年時点の野外に定着しているミシシッピアカミミガメは推定で約800万匹
外来種問題に対する対策として
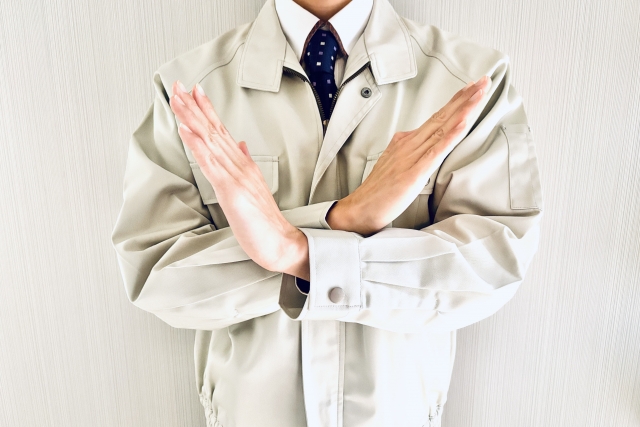
上記の3種にフォーカスして考えてみただけでも、外来種が定着することによって起こる被害はかなりのものです。
外来種に関する問題に向き合っていくためには、様々な角度からアプローチすることができます。
対策の大まかな考え方としては、これ以上外来種を増やさないこと、農作物などを守るために近づけさせないこと、ゆるやかに、もしくは積極的にその個体数を減らしていくことなどが挙げられます。
それらは個人でできることもあればや業者や保護団体などが行う活動であることもあります。
また被害が大きいと認知された場合は自治体や行政が介入し、国を挙げて防除を行う場合もあります。
大前提として…
まず外来種被害対策として覚えておきたいものは、「入れない・捨てない・拡げない」の三原則です。
これは大前提として守っていかないといけないことで、この三原則の普及が最も簡単にできる、しかしとても重要な考え方になります。
今飼っているミシシッピアカミミガメを捨てない、捕まえた外来生物をほかの地域に持ち込まないなど、子供の頃にうっかりとしていたようなことを無くすだけでも、大きな外来種対策となります。
また、外来種を見かけた際には市町村の鳥獣保護課などに一報することも、外来種対策としてはとても有用です。
外来種の保護
外来種を保護して終生飼養することは、そこで繁殖をさせないかぎり緩やかな個体数削減に繋がります。
しかし野生動物として定着している外来種を保護する活動は並大抵の努力でできることではありません。
長らく家畜化されてきた犬や猫の保護もなかなか達成できていない現状を考えると、個体数の極めて多い外来種を保護することはとても難しい活動です。
財源や人員の確保が保護の対象となる個体数に追いつかないからです。
しかし、今回紹介した中でミシシッピアカミミガメは広くペットとして飼養されてきました。
また、まだ条件付特定外来生物であることから特定外来生物よりも法的な拘束力が低く、保護活動が行いやすいといえます。
かめのおうち(正式名称:一般社団法人 TURTLE RESCUE JAPAN)では、一般家庭からのカメの引き取りのみならず、譲渡活動も行っています。
アカミミガメは条件付特定外来生物ですので、不特定多数との譲受け、譲り渡しが禁止されていますが、こちらの団体は必要な届け出を提出し許可を得た上で活動しています。
また、保護団体だけでなく水族館でもミシシッピアカミミガメの引き取りを行っている場所もあります。
以前より神戸市立須磨海浜水族館(現在は名称を改変し改装した須磨シーパラダイスとして営業中)では野生個体や飼育されていたミシシッピアカミミガメを引き取っていました。
須磨シーパラダイスへのリニューアルに伴い、飼育していたミシシッピアカミミガメたちは体験型動物園iZOOに引き取られたのことです。
2024年6月時点で約1000匹のカメが暮らしているといいます。
参考:日本初!体験型動物園iZoo【イズー】|飼いきれなくなった爬虫類を引き取ります
また、アライグマを保護・譲渡していた実績のある野生動物保護団体も存在します。
公益社団法人 神奈川県動物愛護協会では県や市などに依頼されアライグマの保護・譲渡を行っており、東京や横浜、大阪など様々な地域から持ち込まれていたようです。
小さなときに捕獲され、人間に育てられたアライグマが譲渡対象になっているのではと思います。
特定外来生物なので飼養には環境省からの許可が必要で、活動には様々な障壁があるであろうと推測されます。
2025年11月現在では、アライグマの保護活動を積極的に行っている団体は私の調べる限り見当たりませんでした。
外来種の駆除と活用

やはり外来種問題に対する最も効率的な対策はその個体数を積極的に減らしていく駆除に行き着きます。
今回紹介したアライグマやミシシッピアカミミガメは全国に飛散し定着してしまっています。
被害が大きく早急に対策をしていきたいところですが、定着範囲が広ければ広いほど根絶へのハードルは高くなります。
フイリマングースから学ぶ駆除の成功例
日本全土に比べると規模は格段に小さくなりますが、奄美大島に定着していたフイリマングースを根絶できたことは大きな成功例です。
マングース対策を本格的に行うにあたり、マングース対策のためのプロ集団「奄美マングースバスターズ」が結成されました。
この奄美マングースバスターズは当初、環境省から防除事業を受託する一般社団法人自然環境研究センターのプロジェクト専門職員として全国各地から集った12人が雇用されたとのことです。
島内ほぼ全域に渡って高密度にわな(3万個以上)や自動撮影カメラ(300台以上)を設置しました。
当初マングース用のわなは存在せず、イタチ用のわなを改良し、さらに奄美大島の環境に対応したわなを開発するなど本腰をいれて取り組みました。
またマングースの探索犬も導入し、特に捕獲数が減少してからは捕獲犬の効果が発揮されたとのことです。
捕獲作業と並行して、島民への外来種に関する教育活動も行われました。
幾多の困難を乗り越え、試行錯誤のうえ根絶が達成できたのだということが伺えます。
参考:奄美大島における特定外来生物フイリマングースの根絶の宣言について
日本各地におけるミシシッピアカミミガメの対策
ミシシッピアカミミガメは未だ根絶まで道のりが遠い種ではありますが、兵庫県の中南部に位置する稲美町の水辺の里公園では外来種問題の啓発と共にミシシッピアカミミガメを調理し試食する活動が行われています。
さばき方講座も行われており、命を無駄にせず外来種問題に向き合っていこうという稲美町の心意気が伺えます。
参考:地域で取り組むアカミミガメ防除 ~捕獲から死体の有効利用まで〜
また兵庫県の農林水産部のイベントでは鶏のセセリとアカミミガメの食べ比べが行われるなど、県を挙げて普及活動を行っています。
ミシシッピアカミミガメの活用方法は食べることのみならず、農作物に使用するために堆肥化するという方法もあります。
外来種対策は活動者の負担になってしまえば継続することができません。
個人で行うのではなく、地域ぐるみで捕獲から処分、有効利用までを外来種問題の啓発を含めて、楽しく、地域で自立してトータルに行うことが大切であると活動者の方は語っています。
地方自治体を挙げて取り組むアライグマの防除

アライグマに関しては農作物への被害が大きいことから、各自治体の鳥獣保護課などではアライグマ担当室など担当者が置かれていることもあります。
実際のアライグマ防除に関しては侵入状況に合わせた対応が必要で、①未侵入段階、②侵入初期段階、③定着・分布拡大段階、④排除の最終段階の4段階に分けることができるとしています。
ただし②、③、④の段階に関しては捕獲をした上でほとんどの場合駆除を行っています。
アライグマの捕獲に関しては、関連法規の項目で紹介したように狩猟による捕獲と鳥獣保護法による有害鳥獣捕獲、外来生物法による防除の3つの方法があります。
狩猟による捕獲では決められた期間に行う必要があり、わなや銃を用いる場合には狩猟免許が必要です。
有害鳥獣捕獲でも申請先から許可を受けたものが捕獲従事者になることができますが、原則として狩猟免許の取得が前提となるようです。
外来生物法に基づく防除では狩猟免許は不要で、市町村が開催する捕獲従事者講習会を受講した者が捕獲従事者となることができます。
参考:アライグマ防除マニュアル
やはり行政が介入した防除計画に則った活動は、最も駆除のペースが早く効率的だといえます。
しかし防除計画の結果捕獲された外来種は、その殆どがそのまま殺処分されているのが現状です。
そのまま殺処分するだけではなく、食肉として、また毛皮加工や肥料として生まれ変わることができればより効果的な防除になるのではと感じます。
以前の私の記事でも述べたように、日本のフードロスは相当なもので令和3年度では523万トンもの食品ロスが生まれています。
参考:【後進国】日本でアニマルウェルフェアが遅れている6つの理由
また鶏を締める際にはかなりの数が屠殺の段階で廃棄されており、2024年に屠殺方法の不備で廃棄された鶏の数は70万羽にも上ったといいます。
参考:【2025年版】動物愛護法の改正を控えて〜現行法の問題点とは?〜
あまり知られていませんが、アライグマもジビエとして扱われています。
雑食性なのであまり美味しくないのでは…と思ってしまいますが、癖がなく美味だと評されています。
ただし、他のジビエ肉と同じように、よく火を通して食べるよう気をつけてください。
スーパーで販売されている肉を購入するより、日常的にジビエを活用できるようになるほうが、全ての動物たちのためになるのではと思います。
外来種駆除の問題点
外来種であっても一つの命であって、殺すのは可哀想だという意見が出るのはもっともです。
外来種の駆除を行っている当事者も、可哀想だと思いながら活動しているものだと思います。
しかし、広く一般的に駆除を容認してもらうことはやはり容易ではなく、活動の障壁になってしまうものです。
また、殺処分の方法に関して、動物愛護法に記載の「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって」という文言に違反しているのではないかという指摘もあります。
特にアカミミガメの殺処分方法について、冷凍殺と呼ばれる方法が一般的に用いられています。
この方法だと冷凍の段階で体の組織に氷の結晶が形成され、痛みを引き起こす可能性があるとされており、また死に至るまでに時間がかかるということから、残酷な方法だという意見もあります。
特定外来生物に対する様々な検討

特定外来生物に指定されている種はもとの生息地では環境への被害を引き起こさないばかりか、その数が減っているものもあります。
外来種として持ち込まれた国で生息数を減らしたいということであれば、捕まえたあとにそのままもとの生息地まで持っていけばいいのでは、と思う方もいるかも知れません。
(私もそう思いついたうちの一人です)
しかし、数世代に渡って隔絶された個体群を再び引き合わすことによって、遺伝子汚染の発生が懸念されるため現実的ではないようです。
また野生動物の保護活動に関しては先述した通り、並大抵の努力でできることではありませんし、多くの資金が必要です。
突飛な考えですが、在来種にこだわらず外来種も新たな生態系として受け入れていくべきなのかもしれないという意見もあります。
さいごに

ノネコも日本の侵略的外来種ワースト100、世界の侵略的外来種ワースト100に指定されているという事実をご存知でしょうか。
ペットとして人間に愛されているネコも、ひとたび外の世界に出てしまえば生態系に危害を及ぼす外来生物になってしまうのですね。
また、今回紹介したアライグマやフイリマングース、ミシシッピアカミミガメは、原産国においては害獣になどならないばかりか、絶滅が危惧されている場合もあります。
しかし持ち込まれた地域から見るとやはり外来種は元の生態系、生物多様性を脅かしてしまう存在。
一つの種が絶滅するということはその進化の歴史もまるごと消え去ってしまうということです。
殺処分というと反感を買ってしまいますが、外来種が生きていることによって失われていくものもあります。
外来種を殺処分することで失われる命と、外来種をそのままにすることで失われる命ではどちらが多いのでしょうか?
生態系のバランスを保つために個体数の管理は必要不可欠ですが、ただ殺処分するのではなく、有効利用するという選択肢をもっと真剣に考えてみるべきなのかもしれません。
この点にはシカ、イノシシの増加問題や、現在巷を賑わせているクマの問題にも通じるものがあるように感じます。
まだまだ問題は山積していますが、全ては人間の活動が引き起こした結果であり、我々はこの問題について考え続けていく責任があると思います。
この記事が外来種問題について考えるきっかけになれば幸いです。












